オオクワガタの幼虫を大きく育てるためには菌糸ビンが必須です。

菌糸ビンは栄養価の高い広葉樹を粉砕したオガ粉とキノコ菌を用いた幼虫専用の餌です。

菌糸ビンってどれが良いの?いつ使えばいいの?
ちゃんと食べるの?
ご存知ない方は疑問だらけだと思いますので、ひとつずつ紹介します。
菌糸ビンの選び方と用途
菌糸の役割とは?
幼虫はクヌギやブナなどの「オガ」を食べて大きく育ちます。そこに菌糸ビンを使用することで、オガに含まれる成分(リグニンやセルロース)を菌糸が分解し、幼虫が栄養を摂りやすい状態をつくります。そうして、幼虫が食べた後の食べカスやフンにも再び菌糸がまわることで、常に栄養が摂れるサイクルができます。

よって、幼虫を大きく育てるためには、菌糸ビン飼育が最も適しています。
菌糸の選び方
菌糸に使用するオガは栄養価の高いクヌギや分解の早いブナ等を使用しますが、幼虫の成長に大きく関わるのが、オガを分解する菌糸です。菌糸の種類と特徴を知ることで、ブリードの知識として非常に役立ちます。
菌糸の種類
オオクワガタの幼虫飼育に適している菌糸の種類は主にオオヒラタケ、ヒラタケ、カンタケの3種類、そして産卵に適しているカワラタケになります。それぞれ異なるメリット・デメリットがありますので、順に紹介します。
オオヒラタケ

オオヒラタケは高温に強く、幼虫の餌の食いつきが良いです。また、菌糸交換の際に幼虫が暴れたとしてもすぐに菌糸が再生してくれるので、初心者の方にもオススメです。
オススメ品
月夜野きのこ園様の【Element】がオススメです。それなりにサイズがでて、安定した供給に価格もリーズナブル!
9ブロックまとめ買いだと送料無料になるのでお財布にも優しいです。
また、大型狙いにはEXCEED CRAFT様のGSPや銚子オオクワガタ倶楽部様のCSがオススメです。

オオヒラタケをもっと知りたい方へオススメの記事です☺
ヒラタケ
ヒラタケはオオヒラタケに比べて水分量が少ないので、劣化しにくいです。
ちなみにヒラタケの仲間にカンタケがあり、戸惑いがちですが別物になります。
オススメ品
カンタケ
超大型の羽化を狙うのにオススメの菌糸です。多湿だと劣化しやすく、菌糸ビン作成の際は菌糸を生成するために酸素を多く消費するので、菌糸ビンを裏返してガス抜きしたり幼虫への餌の食いつきをみたり等、ヒラタケ系に比べると少々難易度高めの菌糸です。その分栄養価が非常に高く、幼虫体重が乗りやすいので、オススメです。
オススメ品
三階松きのこ農城様のtype-555tは非常に人気があり、レコードホルダーもこの菌糸を使用しています。うまくブリードできると、幼虫体重がかなりのるのでサイズだけでなく、イカツさが売りの川西産にも相性バッチリの菌糸です♪
また、神長キノコ園様のS8カンタケも有名でオススメです。専用サイトでの販売になりますが、非常に人気があるため品切れになりやすいです。
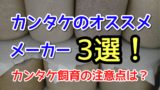
カンタケをもっと知りたい方へオススメの記事です☺
カワラタケ
カワラタケは、オオクワガタの産卵に適しています。通常は産卵木に産卵しますが、菌糸カワラ材は♀の産卵意欲を促進します。
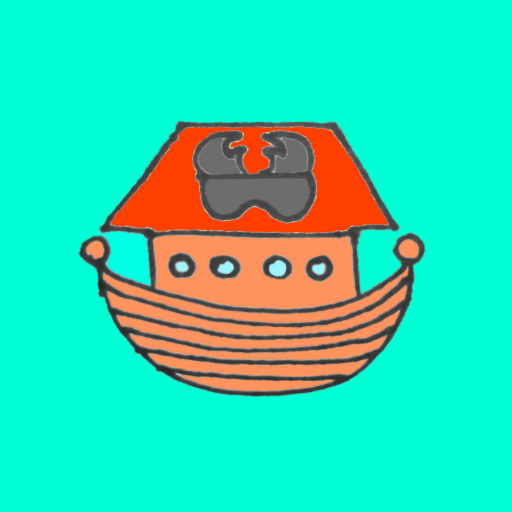
オオクワガタには体内時計があり、産卵時期は3月中旬〜遅くても9月までです。
カワラタケはオオクワガタの幼虫育成には不向きですが、タランドゥスオオツヤクワガタやオウゴンオニクワガタ等、外国産のクワガタ飼育には向いています。
オススメ品
産卵用のカワラ材になります。菌糸でできた白い被膜がありますが、剥く派と剥かない派で分かれます。僕としてはどちらもメリットがあり、正解と思うので状況に応じて使い分けています。
親が食べていた菌糸
ここで、菌糸選びのポイントです。
幼虫も菌糸の好き嫌いがあり、良い菌糸でもほとんど食べずに体重が乗らない場合があります。そんな時は、親がどの菌糸を食べていたかチェックして下さい。
基本的に親と同じ菌糸であれば食べますので、気になる際は親種の飼育管理表を参考にして下さい👀
菌糸ビンの温度と湿度管理
菌糸ビンを使用して幼虫を大きく育てるには、
温度と湿度が重要です。
せっかく菌糸ビンで育てているのに常温だと高確率で小さい成虫になります。
常温管理のデメリットは、
・温度が高いとオオクワガタが早期羽化する
・温度が15℃以下だと、幼虫が餌をほとんど食べない
このように菌糸だけでなく、幼虫の成長に影響を及ぼします💦
最も簡単な温度管理方法はエアコンですが、小規模であれば冷やし虫家がオススメです。

僕は幼虫飼育に冷やし虫家を3台で管理しています。冷やし虫家は1時間あたりの電気代が約1円なので、電気代が安く、長期で温度管理するにはオススメです。空調機器が故障した際も新品は1年のメーカー保証(シーラケース)がついて、それ以降の故障でも1万円程で修理して頂けます!
小規模で幼虫飼育される方にオススメです♪
続いて湿度ですが、多湿だと菌糸が泥状になり、劣化しやすくなります。

最適な湿度は60%台ですが、梅雨時期は多湿になりやすいので除湿剤があると便利です。
菌糸ビンの投入時期と交換
菌糸ビンの投入時期はブリーダー様によって異なります。大型を狙いで初令から菌糸ビンに投入することもあります。ですが孵化したては菌糸に負けてしまう恐れがあります。なので、初齢から菌糸へ投入する時は幼虫の頭に色がついてから投入した方が良いです。
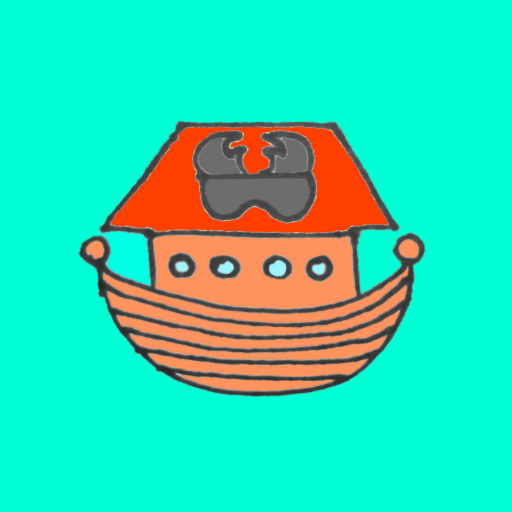
菌糸ビンの交換時期は3ヶ月に1回が目安です。
オオクワガタは生まれてからおおよそ1年で成虫になるので、菌糸ビンは計3回〜4回交換します。
菌糸ビンのサイズですが、
800cc、1100cc、1400ccが主です。
僕の場合、以下にて菌糸を詰め替えてます。
♀ 800cc・800cc・800cc
菌糸は販売元よりたくさん種類があります。オススメは月夜野きのこ園様のEブロック(オオヒラタケ)です。
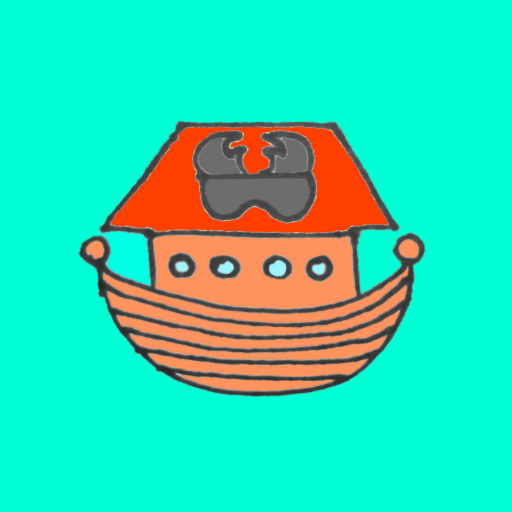
それなりにサイズがでて、まとめ買いだと送料無料になるので、お得です☺
正直な所、菌糸ビンって単価が高いですよね😓
ですが、菌糸ブロックから菌糸を詰めると…
菌糸ビンの4分の1の価格に抑えれます。
手間はかかりますが、とても経済的なのでオススメです(^^♪
♂と♀の見分け方
♂と♀は特徴の違いが2つあります。
卵巣の有無
初令で見分けるのは困難ですが、♀の場合、2令になると幼虫のお尻の部分にオレンジ色の丸い斑点(卵巣)が確認できます。
幼虫の体重
初令ではほとんどわかりませんが、2令以降は体重差が出ます。
参考までに、♀の幼虫の最終体重は20g無いくらいです。もし、20g超えていたら大型で羽化する期待大です!
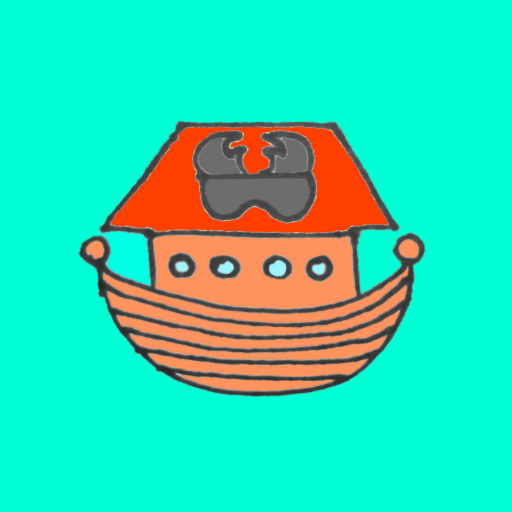
2本目の菌糸交換時は幼虫体重に差がでるので、性別を判別しやすいです♪
菌糸ビンに幼虫を投入する

菌糸ビンに投入するときは、幼虫が菌糸に入りやすいように菌糸の上部から中央にかけて穴をあけます。

僕は幼虫のサイズに合わせてマキタの電動ドリルで菌糸ビンの穴を空けます。
菌糸ビンに移す際の注意点
幼虫を菌糸ビンに移す際、傷ついて体液が漏れてしまうと残念ながら☆になります。

幼虫が☆になると、このように真っ黒になりますので、幼虫が傷つかないように十分注意してください。
また、蛹になる直前(前蛹)若しくは蛹の状態で、菌糸交換で蛹室を壊してしまうとそのままだと羽化不全のリスクが高くなるので、その際は人口蛹室に入れ替えて下さい。
幼虫の暴れについて
菌糸を交換後に菌糸の酸素が足りていなかったり、幼虫に菌糸が合わなかった場合、菌糸ビン交換後の幼虫は中で動きまわります。

これを「暴れ」といいます。一見たくさん食べて良さそうに見えますが、実はその反対でせっかく体重の育った幼虫が暴れることで体力を消耗して幼虫体重が落ちます。
上記の画像ではそこまで暴れてませんが、幼虫が菌糸ビンの周りを2周くらい這うように食っていたら暴れと判断します。菌糸は数日すると再生するので、菌糸が再生されずに暴れ状態が続くと対策が必要です。
逆に、菌糸ビンの周りが真っ白な状態だと幼虫が体力を消耗せず、その場でじっと菌糸を食べている可能性が高いです。これを「居食い」といいます。居食いの状態が続くと幼虫に体重がのりやすいです。

大型を狙うには幼虫の暴れを防いで、居食いさせることがポイントです♪
まとめ
菌糸の良い選び方と管理方法は?
・菌糸ビンの温度と湿度を徹底
・3ヶ月に1回菌糸ビンを交換
・幼虫を暴れさせない
以上です。
大型での羽化を狙うには、手間がかかりますがそれが幼虫飼育の醍醐味だと思います☺
最後に、クワガタのブログランキングに挑戦中なので、⇩をクリック頂けるとめっちゃ嬉しいです😆!
にほんブログ村
それでは(^^♪
川西!!

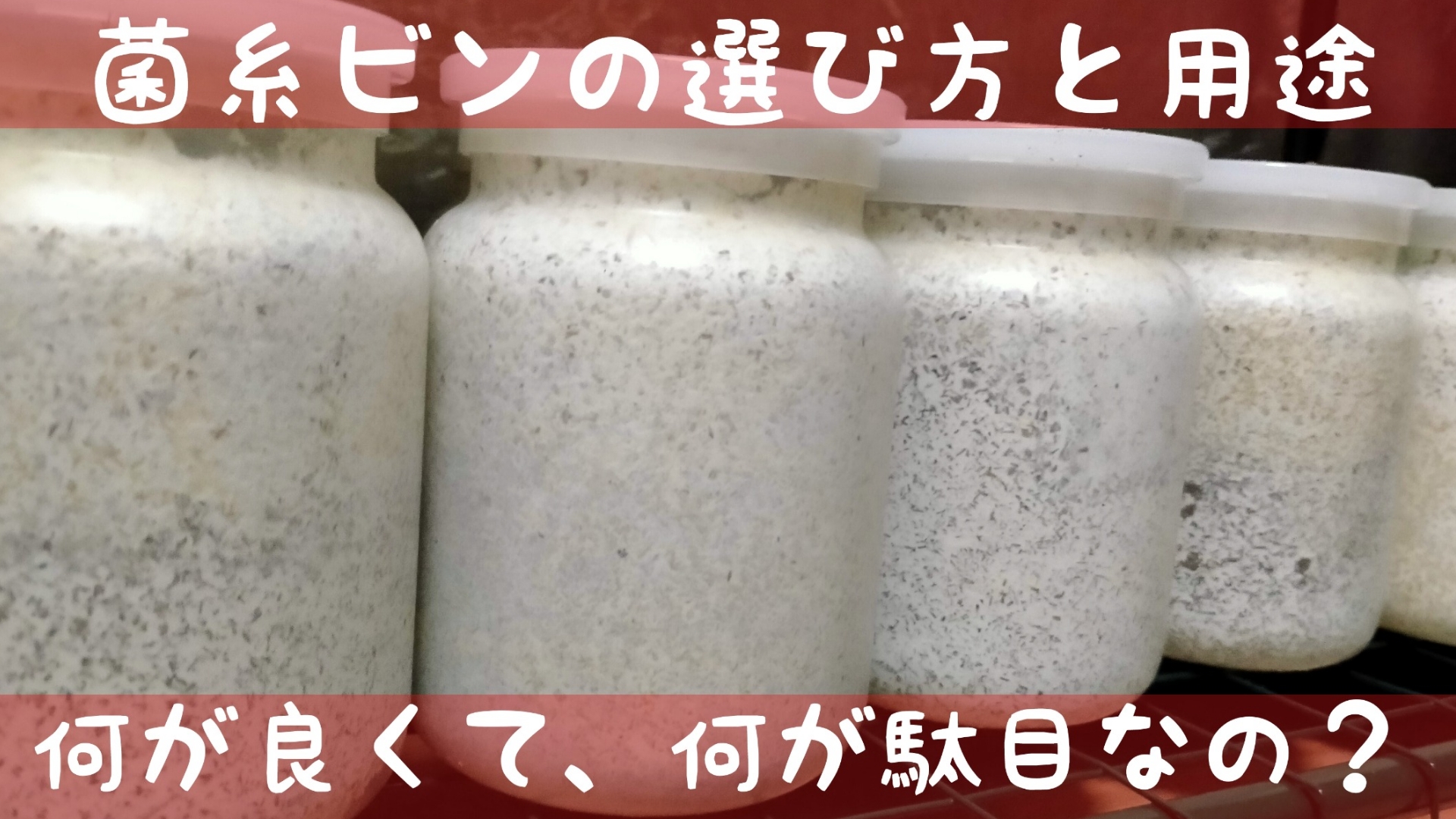
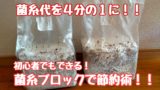


コメント